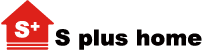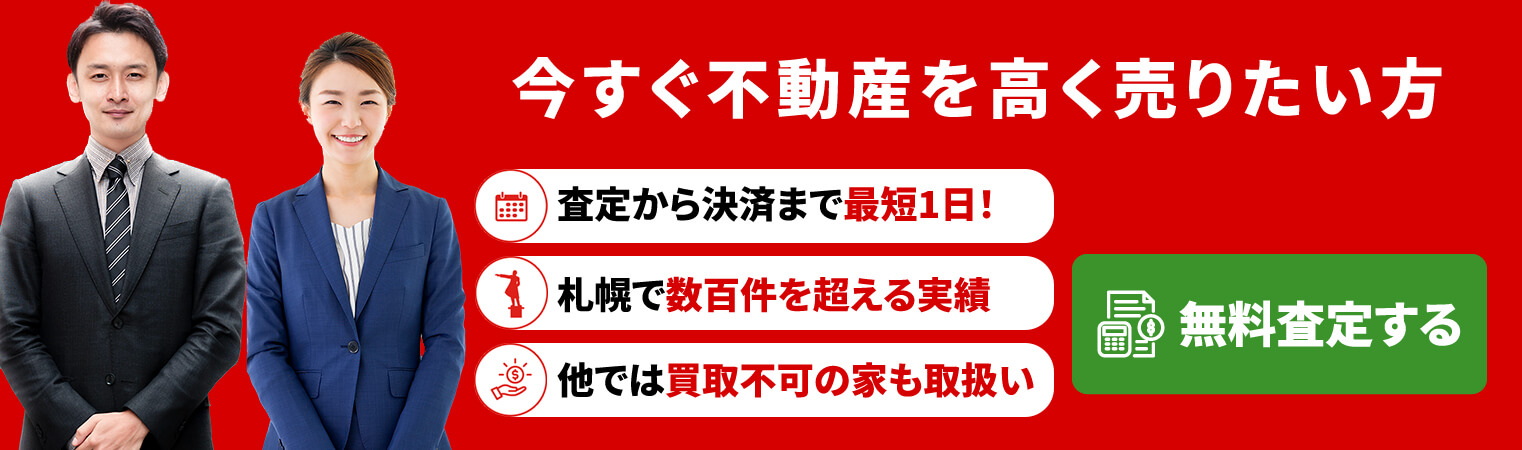目次
減価償却費とは
不動産における「減価償却」とは、所有する固定資産(例えば、建物や機械設備など)が年数の経過によって劣化していったり、価値が減少していく分の金額を、購入費用から減らしていく会計処理のことです。
例えば、1,000万円の建物を購入して10年にわたって使用した場合、1,000万円を初年度に全額計上すると、翌年度からは収益だけが発生することになってしまいます。経費に計上するのは、その会計年度に使用した分なので、1,000万円を10年(正しくは定められた法定耐用年数)で割り、一度資産として計上した後に費用として振り替えていくというのが基本です。償却期間として定められた複数年にわたって、毎年決められた費用を計上していくため、経済状況が把握しやすくなるメリットがあります。
これは、あくまでも会計上のルールとしての費用なので、実際の建物の減耗や劣化に相当する金額でもなければ、その分の代金支払いを必要とするものではありません。
支払いがないにも関わらず、帳簿上は経費として計上できるため、節税の手段としても利用されています。
減価償却を活用する場面
減価償却を活用するのは、主に「不動産投資」や「不動産売却」の際です。
まず、不動産投資で収入を得た場合は、所得税と住民税が課税されます。この所得税は、所得金額に応じて税率が上がる累進課税制度となっているため、利益額が大きくなるほど税負担も大きくなります。そのため、経費として計上できる減価償却費は、節税につながる重要な要素となるのです。
また、不動産売却で利益が出た場合には、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は、以下の計算式で「譲渡所得」を計算し、それに税率をかけて算出します。
譲渡所得=売却金額−(取得費−減価償却費)−譲渡費用−特別控除
取得費とは、不動産を購入した当時の費用のことで、購入代金はもちろん仲介手数料などの諸費用も含まれます。譲渡費用は、不動産を売却する際に生じた仲介手数料や印紙代など様々な諸費用のことを指します。特別控除とは、一定要件を満たしたマイホームを売却したり、相続で取得した建物を売却したりした際に適用される控除のことを指します。
取得費を計算する際には、資産価値の減少を加味するため、これまで経費として計上した減価償却費を差し引かなければなりません。そのため、多くの減価償却費を計上している場合は、取得費が低くなることで譲渡所得が大きくなるので注意が必要です。
なお、土地の取得費がわからない場合は「売却金額の5%」を取得費として計算することになっています。これは、実際の取得費が5%に満たない場合にも活用できるものなので、減価償却によって取得費が低くなったときに活用してみると良いでしょう。
不動産投資の減価償却費の対象
前述のとおり、不動産投資において減価償却費の対象となるものは「建物および付帯設備の価格」です。建物や付帯設備は時間の経過とともにその価値が減少するため、会計上で減価償却費として計上できます。これは、建物や設備が使用されることで劣化し、修繕や交換が必要になるためです。具体的には、建物の構造部分、屋根、壁、床、配管、電気設備などが減価償却の対象となります。
ここで注意が必要なのは、不動産投資において「土地部分については減価償却を行う必要がない」ということです。減価償却の対象となるものは、あくまでも時間が経つにつれて価値が下がっていく資産であり、すべての資産を減価償却できるわけではありません。
実際の土地価格は、市況によってその時々で変化がありますが、会計上、土地は年数の経過に関わらず、使用によって価値が減少することがないと考えられるためです。土地の借地権なども同様です。
そのため、不動産の減価償却は「建物価格」と「土地価格」を分けて、建物価格にのみ減価償却を行います。具体的には、購入価格のうち建物部分の価格を減価償却の対象とし、土地部分の価格は対象外とします。例えば、総額1億円の不動産を購入し、そのうち建物が7,000万円、土地が3,000万円と評価される場合、減価償却費として計上できるのは建物部分の7,000万円のみです。
不動産投資の減価償却期間
不動産投資の減価償却期間は、法定耐用年数と築年数から定められています。対象となる不動産を新築で購入した場合と中古で購入した場合で異なりますので、それぞれ解説していきます。
新築で購入した不動産の場合
まず、法定耐用年数は、建物の用途や構造によってそれぞれ定められており、新築の場合は下記表の年数がそのまま法定耐用年数となります。
表に記載した以外にも、レンガ造や金属造などの構造、ホテルや工場などといった用途にも法定耐用年数が定められています。必要な方は国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」をご参照ください。
| 用途 | 構造 | 法定耐用年数 |
| 住宅用 | 木造 | 22年 |
| 木骨モルタル造 | 20年 | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
47年 | |
| 事務所用 | 木造 | 24年 |
| 木骨モルタル造 | 22年 | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
50年 | |
| 飲食店用 | 木造 | 20年 |
| 木骨モルタル造 | 19年 | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
34年 ※延べ床面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの |
中古で購入し、築年数が法定耐用年数の一部を超えている場合
中古で購入し、築年数が経過している場合は、上記の表で掲載した法定耐用年数から経過年数を引き、下記の計算式にあてはめて算出します。
耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
例:築10年の鉄骨コンクリート造物件を購入した場合の耐用年数
(47年-10年)+10年×20%=耐用年数39年
中古で購入し、築年数がすでに法定耐用年数を超えている場合の耐用年数
上記に記載した法定耐用年数一覧表の該当法定耐用年数を用いて、下記の計算式で算出します。
耐用年数=法定耐用年数×20%
例:築25年の木造物件を購入した場合の耐用年数
22年×20%=耐用年数4年
減価償却費が節税になる理由
減価償却費で負担を減らせる税金とは
冒頭でもお伝えしましたが、減価償却費は、実際の支出を伴わない会計上のルールとしての費用なので、実際の建物の減耗や劣化に相当する金額でもなければ、その分の代金支払いを必要とするものではありません。
支払いがないにも関わらず、帳簿上は経費として計上できるため、節税の手段としても利用されています。減価償却費で負担を減らせる税金は、主に法人税や所得税です。法人税や所得税などは、所得に対して課税される累進課税制度を採用しているため、所得が多ければ多いほど、税額が増える仕組みになっています。減価償却費を法定耐用年数に応じて分割計上することで、課税対象となる所得金額を少なくすることができ、長年にわたって節税につながるというわけです。
また、購入金額が10万円未満の資産の場合は、耐用年数が1年未満であれば、少額減価償却資産として取得した年度に経費計上することができるので、活用すればさらに納税額を減らすことができます。
損益通算による所得の赤字と黒字の相殺
所得税・住民税については、「損益通算」を行うことで、課税対象の所得額を少なく申告できるため、毎年の納税額を抑える効果を期待できます。
不動産投資において生じた赤字は、自身の給与所得などの黒字と相殺することが可能です。所得税や住民税の税額は、給与所得やその他の収入から不動産投資の赤字分を差し引いた金額をもとに算出されます。これを損益通算といい、課税対象から控除される金額は、以下の式で求められます。
不動産投資以外の収入から差し引くことができる赤字額=家賃収入–必要経費
減価償却と併せて損益通算を行えば、不動産投資の納税額をさらに抑えることが可能です。たとえば、1年間の家賃収入が300万円、購入費用の減価償却費が500万円、その他経費が100万円であれば、300万円-500万円-100万円=-300万円となり、赤字額300万円分が損益通算されることになります。
年収が1000万円の人であれば、損益通算を行うことで1000万円(年収)-300万円(赤字額)=700万円として所得額を申告できるため、所得税と住民税の負担を減らすことにつながります。
つまり、減価償却費が大きければ大きいほど、会計上の赤字を大きくすることができるため、より所得額を少なくすることができ、節税効果が高まります。
減価償却費を利用して節税する際の注意点
長期間にわたる不動産所有のリスク
先ほども記載しましたが、減価償却を行うことができる期間は、不動産の法定耐用年数と築年数から定められています。長期間にわたって不動産を所有していると、いずれ収入から減価償却費を差し引けない時期がやってきます。
期間満了後は、減価償却費を経費として計上できなくなるため、当然不動産投資の黒字が増えて、その分所得税額も上がり、資金繰りの悪化につながります。また、耐用年数を大幅にすぎた物件は、投資用としても居住用としても需要が低下し、買い手が見つかりにくくなるリスクもあるため、耐用年数の範囲内で売却してしまうことも視野にいれておきましょう。
譲渡所得税の負担が増える点に注意
逆に、投資用不動産の早期売却も、支出を大きく増やしてしまうリスクがあるので、注意が必要です。個人による不動産の売却利益には譲渡所得税がかかり、その税率は物件の所有期間に応じて異なります。取得から5年以内に売却する場合は「短期譲渡所得」、5年を超えてから売却する場合は「長期譲渡所得」の税率が適用されます。
| 不動産の所有期間 | 譲渡所得税率 |
| 所有期間が5年を超える(長期譲渡所得) | 20.315% |
| 所有期間が5年以下(短期譲渡所得) | 39.63% |
表の通り、短期譲渡所得の税率は、長期譲渡所得の約2倍に設定されています。
例えば、不動産譲渡所得が800万円の場合で計算してみると、譲渡所得税額の違いがお分かりいただけると思います。
| 不動産の所有期間 | 計算式 | 譲渡所得税 |
| 所有期間が5年を超える(長期譲渡所得) | 800万円×20.315% | 1,625,200円 |
| 所有期間が5年以下(短期譲渡所得) | 800万円×39.63% | 3,170,400円 |
このように、売却を急ぎ過ぎることで、所得税の負担が増えるので注意が必要です。