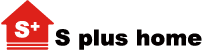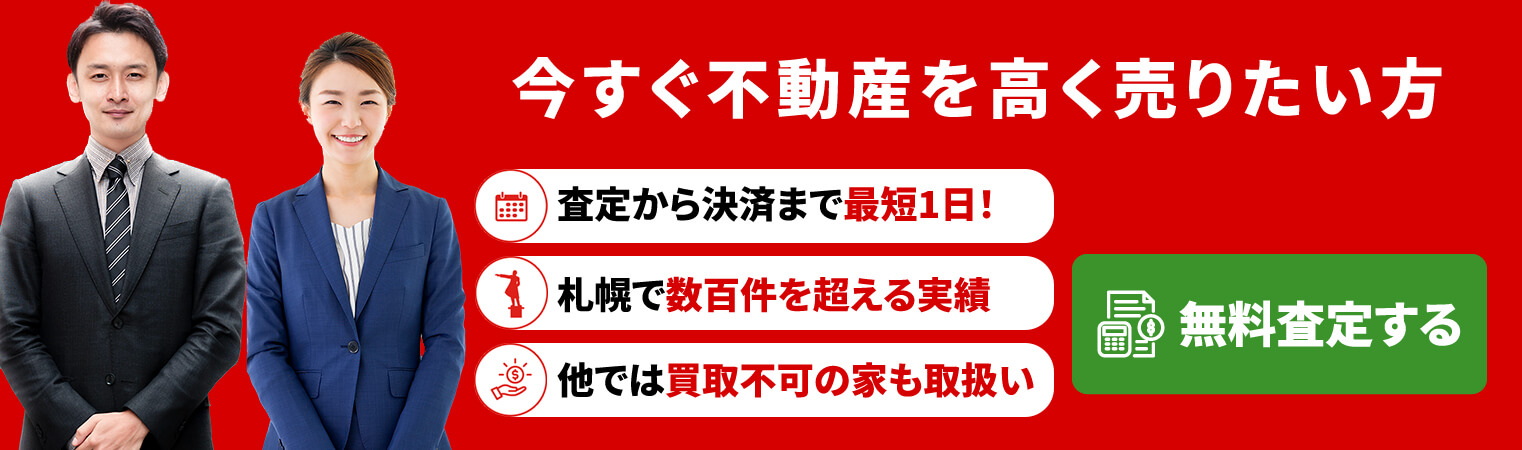アパートを相続する際には、物件の所在地や法的なルール、相続税の計算方法など、多岐にわたる知識が必要となります。
特に札幌でアパートを所有・運用している場合、地域性や不動産市場の動向も押さえる必要がありますし、相続時には「借地借家法」が関係してくる場合があり、これを理解しておくと相続税評価の面で思わぬメリットを得られる可能性があります。
本記事では、不動産の初心者の方でもわかりやすいように、札幌でアパートを相続する際の基本的な流れや借地借家法の概要、そして相続税評価との関係について解説します。
借地借家法の概要
法の目的
借地借家法は、その名のとおり「土地を借りる(借地)」「建物を借りる(借家)」際のルールを定めた法律です。
1991年に従来の借地法・借家法を一本化する形で制定され、主に借主の居住や建物所有の安定を図ることを目的としています。
大きな特徴として、借主は正当事由がない限り契約を更新拒絶されにくく、家主が一方的に退去を求めることも難しいという点が挙げられます。
住宅を借りる方々にとっては、突然の立ち退きを回避し、長期間にわたって安心して居住できる仕組みを整えているのです。
借地権の定義
借地借家法では、建物を所有することを目的に他人の土地を借りる権利を「借地権」といいます。
例えば、一戸建てを建てるために土地を借りる場合や、自分が所有する店舗を建てるために土地を賃借する場合に適用されます。
旧借地法(現行の借地借家法が施行される前)からある従来型の借地権は、借主が非常に強い権利をもっており、地主が土地を取り戻すには正当事由に加えて多額の立ち退き料が必要になることが一般的でした。
現在でも、更新料や承諾料など借主・地主双方で取り決めを行うことが多く、契約関係は複雑化しがちです。
相続においては、借地権も財産の一部となり、相続税評価の対象となる点に注意しましょう。
借家権の概要
借家権とは、建物を借りる(賃借する)権利のことです。
これは、アパートやマンション、戸建てなどに居住する際に結ぶ賃貸借契約によって生じる権利を指します。
借地権が土地の賃借を中心に扱うのに対し、借家権は建物の賃借が対象となるため、性質が異なります。
借地借家法における借家のルールは、契約期間や更新、解約などについて詳しく定められています。
特に居住用建物の場合、借主が強く保護されており、オーナーが契約更新を拒否するには「正当事由」が必要です。
家賃滞納などがない限り、オーナーの都合だけで契約を終了させるのは容易ではありません。
借地借家法とアパート相続の関係
借家権割合とは
借家権割合(または借家権比率)とは、借家人が有する権利を金額面で評価する際に用いられる割合です。
オーナーが所有する物件に対し、借家権という負担がついていることで、市場価値がどの程度下がるかを示すものです。
例えば、自用の建物(オーナー自身が住んでいる建物)に比べ、賃貸アパートなどは借主の保護があるため、オーナーが勝手に取り壊したり、売却したりすることが難しくなります。
この制限がある分だけ、物件の評価額は下がり、その下がる分を数値化したものが借家権割合です。
国税庁の通達では、一律で30%などと定められているケースがありますが、地域や契約状況によって異なる場合があるため、具体的には専門家に確認するとよいでしょう。
相続税評価額との関係
借地借家法に基づく借地権や借家権が設定されている場合、一般的に不動産の評価は低くなります。
これは相続税の計算においても同様です。
特にアパートを相続するケースでは、「貸家建付地」として土地や建物が評価されることが多くなります。
貸家建付地とは、他人に建物を貸している土地のことで、オーナー自身が自由に利用できないことが評価減の根拠となります。
借家権割合も相続税評価額を計算する際に重要な指標であり、借家人の権利が強く保護されている分、自己居住用物件よりも評価額が下がる仕組みです。
計算例
仮に札幌市内にあるアパート(敷地面積200㎡、固定資産税評価額1,000万円、借家権割合30%)を相続する場合、評価は次のようなイメージで行われます。
・更地としての評価額を算出
・借家権割合や賃貸割合(実際に入居があるか)を考慮して減額
・建物部分も固定資産税評価額をもとに貸家評価を行い、同様の減額を適用
最終的に、更地や自用の建物として評価した場合よりも低い評価額となり、相続税の課税額が軽減される可能性が高まります。
札幌の借地借家法・借家権と相続税対策としてのメリット
相続税評価が減額
札幌市は人口が集中しており、賃貸需要も比較的安定している地域です。
アパート経営において、借家権が設定されていることで相続税評価額が減額されるのは、オーナーにとって大きなメリットとなるでしょう。
自己使用の住宅や更地に比べ、借家という形で第三者に貸している物件は、オーナーの自由に利用できない制限があるため、評価額が下がる仕組みになっています。
結果として相続税を支払う際の負担が軽くなる可能性があり、これから相続が発生する見込みがある場合は、あらかじめ賃貸契約の有無や契約内容を整備しておくと、スムーズに評価減を受けやすくなります。
小規模宅地等の特例を適用できる可能性
相続税には、被相続人が居住していた土地や事業用の土地などに対して「小規模宅地等の特例」が設けられています。
一定の要件を満たすことで、土地の評価額が大幅に減額される制度です。
賃貸アパートの用地にも、この特例が適用される可能性があります。
ただし、この制度には「事業的規模で賃貸事業を営んでいたか」など、細かい要件があります。
また、もともとの借地借家法による評価減がある場合、さらに小規模宅地等の特例を併用すると相続税評価額が一層下がる可能性もありますが、同時に控除額が制限されるケースもあるため、専門家の確認が必要です。
入居者駐車場の扱い
アパート運営では、敷地内や近隣に駐車場を設けて入居者に貸し出すことが多くあります。
この入居者専用駐車場も、賃貸アパートと一体的に利用されている場合には、借家権割合が適用されるケースがあります。
駐車場部分だけが独立していると、評価の仕方も変わってくるため、相続税を計算する際には「アパート敷地の一部として賃貸借契約に含まれているかどうか」をしっかり確認しましょう。
札幌のように車社会の地域では、駐車場の有無が入居率にも影響します。
相続後に運営を継続する予定があるなら、駐車場契約も含めて書類を整えておくとよいでしょう。
借地借家法は、土地や建物を借りる人の権利を強く保護する法律であり、アパート運営を行うオーナーにとっては、物件を自由に扱いづらくなるというデメリットもあります。
しかし、相続時にはこうした制限がある分不動産評価額が下がり、相続税の負担が軽減されるというメリットが生まれます。
札幌でアパートを所有し、将来的に相続の可能性がある場合には、この借地借家法による評価減をうまく活かすことで、家族全体の納税負担を抑えられる可能性が高いでしょう。
また、小規模宅地等の特例など、相続税対策として利用できる制度は複数存在します。
自分の物件がどの特例に該当し、どのくらい評価減を受けられるのかは、物件規模や契約形態、立地条件などによって変わりますので、早めに税理士やなどのプロへ相談することをおすすめします。
さらに、入居者専用の駐車場もアパートの一部とみなされる場合があり、借家権割合の適用によって評価が下がることがあります。
札幌のように車の利用が多い地域では駐車場の需要も高いため、物件運営と税務上の評価を両立するために、賃貸契約書をはじめとする各種書類をきちんと整備・保管しておきましょう。
相続は家族にとって大きなライフイベントであり、特に不動産に関する知識がないと手続きが複雑に感じられるかもしれません。
札幌でアパートを相続する予定がある方は、ぜひ本記事を参考に、今から準備を始めてみてください。