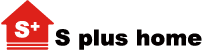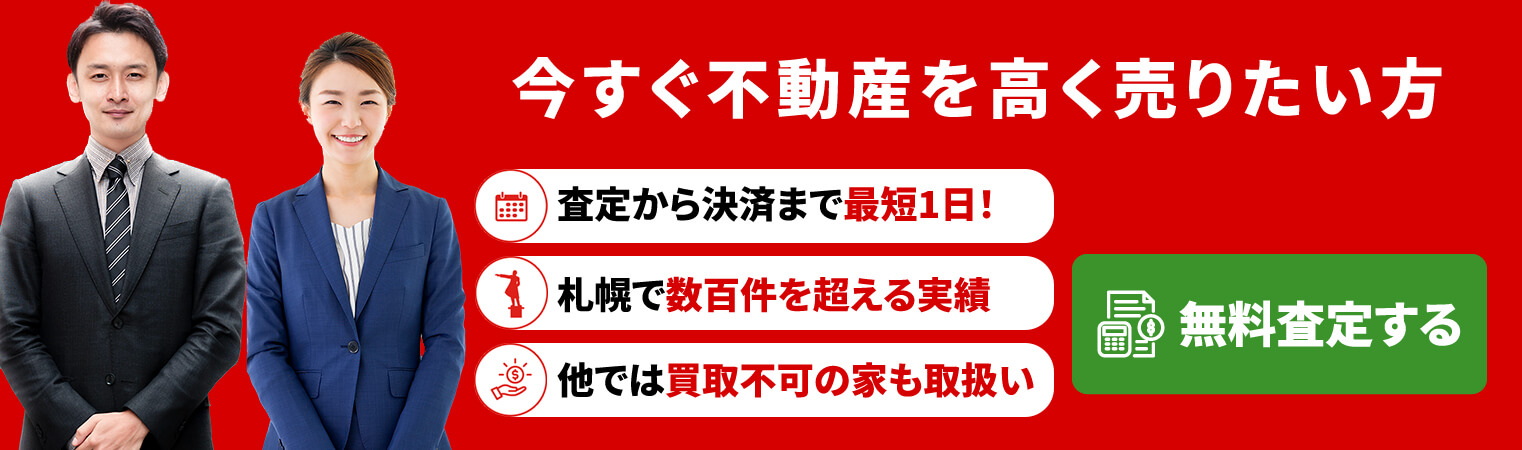目次
生前贈与とは
「生前贈与」とは、個人が生存中に自らの財産を他人に無償で譲渡する行為のことです。これは、財産を持っている個人が亡くなった後に行われる「相続」とは異なり、贈与者が生きている間に行うため、贈与者の意思に基づいて誰にでも財産を渡すことができるという特徴があります。
相続:
被相続人の死亡に伴い、その財産が法定相続人に分割される制度であり、遺言や法律に基づいて進行。
生前贈与:
贈与者が自由に財産を譲り渡す相手を選ぶことができ、相続が発生する前に計画的に財産を譲渡する手段。
後ほどの章で詳しく解説していきますが、生前贈与には相続税を節税できるなどのメリットがある一方、贈与税がかかるなどのデメリットも存在します。手順やタイミング次第では、税金の負担が増えたり、親族間のトラブルにつながる可能性もありますので注意が必要です。
生前贈与の手続き
生前贈与を行うためには、以下の4つの流れで手続きを進めていきます。
贈与の内容や方法を決める
まずは、誰に何を贈与するのかを決めましょう。贈与の目的や財産の使い道によっては非課税制度が適用になる場合もあります。また、贈与税の課税方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2種類がありますので、それぞれ比較してどちらを選ぶが決めておくと良いでしょう。
贈与契約書の作成
贈与する人と贈与を受ける人との間で贈与契約書を作成します。これは、贈与の意思を明確にするための重要な文書であり、贈与の内容や条件、日付などを記載し、実印での押印が必要です。たとえ家族間の生前贈与であっても、のちのち何らかのトラブルになる可能性もありますので、作成しておくのが確実です。贈与が基礎控除内で収まるケースも同様に作成しましょう。
贈与する財産を移す
金銭を贈与する場合は、贈与の事実を証明できるように銀行振込で行います。
土地や建物など不動産を生前贈与する場合は、贈与後に不動産の名義変更を行うための登記申請が必要になります。贈与する不動産を管轄する法務局で、所有権移転登記の手続きを行いましょう。名義変更手続きには以下の書類が必要になり、申請後1〜2週間で登記が完了します。
【不動産名義変更の必要書類】
・贈与契約書
・贈与する不動産の登記識別情報通知(登記済権利証)
・贈与する人の直近3ヶ月以内に取得した印鑑証明書
・名義変更をする年度の固定資産税評価証明書
・贈与を受ける人の住民票
贈与税の申告
生前贈与には贈与税が課されるため、贈与税の申告を行う必要があります。
先ほど贈与税の課税方法には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2種類あるとお伝えしましたが、以下それぞれについて記載しておりますのでご参照ください。
どちらも申告は、贈与が行われた翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告書を提出し、納税を行います。
「暦年贈与」の場合
1年間(1月1日〜12月31日までの間)で、総額110万円を超える贈与を受けた場合に申告が必要になります。110万円以下であれば金銭だけでなく、土地や建物などの不動産も含まれます。
「相続時精算課税」の場合
贈与者1人につき2,500万円までは特別控除、さらに2024年1月の法改正により年110万円までは基礎控除が受けられます。
改正前の相続時精算課税制度は、少額の贈与でも贈与税の申告が必要でしたが、今回の改正によって年110万円以下の贈与については申告が不要となりました。
不動産の生前贈与のメリット
贈与する相手やタイミングを選べる
生前贈与の大きなメリットは、贈与者が自分の意思で贈与する相手やタイミングを自由に選べることです。相続の場合、遺産分割の際に法定相続人が関与し、法律に基づいた手続きが必要となるため、遺留分が生じたり遺産分割争いに発展してしまったりなど、贈与者の意図に反する結果になる可能性もあります。一方、生前贈与では、特定の相手に特定の財産を確実に譲り渡すことができ、贈与者の意思を尊重した財産移転が可能です。
相続財産が減少することで相続税の軽減に繋がる
計画的に生前贈与を行うことで、相続税の節税につながるケースがあります。例えば、年間110万円までの基礎控除がある暦年贈与は、長期間にわたって利用することが可能なので、年齢の若いうちから贈与を始めることで節税効果が高くなります。
また、相続時精算課税制度において、不動産や株式などの相続税は、贈与時の評価額・時価によって計算されるため、将来的に値上がりが確実な財産であれば相続税の節税になり得ます。
注意が必要なのは、相続時精算課税の贈与では相続税が非課税にはならないということです。例えば、相続時精算課税の特別控除を利用して2,500万円の不動産を贈与した場合、贈与した年に贈与税は課税されませんが、贈与者が死亡した際には2,500万円が相続財産となり、相続税が課税されることになります。
収益物件の贈与で相続税対策が可能
賃貸マンションやアパートなどの不動産や配当利回りがよい株式などの収益性がある財産の場合は、不動産の賃料や株式の配当金などの収益を、贈与を受けた人が贈与以後から受け取ることができ、当然それらの収益は贈与を受けた人の所得となります。それにより、贈与する人は賃料や配当金など収益による現預金の増加を抑えることにつながります。現預金は贈与者が亡くなったときには相続財産になりますので、収益の分だけ相続税の節税につながります。
贈与税の軽減特例も活用できる
通常、生前贈与には贈与税がかかりますが、特例を活用できれば負担を軽減することができます。例えば、婚姻期間20年以上の夫婦間であれば、一定の要件を満たすことで「贈与税の配偶者控除の特例」を利用できます。配偶者に対し住宅取得のための資金を贈与や居住用不動産の贈与をする場合、2,000万円まで贈与税が非課税となります。
また、2026年12月末までに父母や祖父母などから新築住宅などのために資金を贈与された場合、要件を満たせば一定額まで贈与税がかからない住宅取得等資金の贈与の特例もあります。一定額とは、一定の耐震性・省エネルギー性またはバリアフリー性などを有する住宅用家屋については1000万円、それ以外は500万円まで贈与税が課税されません。
この他、贈与には「結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置」「教育資金の贈与税の非課税措置」など様々な制度があります。それぞれ個人の状況次第で利用できるものが異なりますので、相続に強い税理士に早めに相談をすると良いでしょう。
不動産の生前贈与のデメリット
贈与税の負担
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内での贈与であれば贈与税がかかりませんが、それを超える贈与には贈与税が課されます。贈与税の税率は相続税の税率より高く設定されているため、生前贈与を無計画に行うと贈与税の負担が大きくなり、結果として相続税よりも高い税金がかかる場合があります。
そのため、生前贈与を行う際には、贈与税の課税範囲や利用できる特例措置などを十分に理解し、計画的に贈与を行うことが重要です。
不動産所得税と登録免許税の負担
贈与税や相続税以外に、生前贈与で不動産を贈与した場合、贈与を受けた人には不動産所得税と登録免許税が課されます。生前贈与での不動産所得税の税率は、固定資産税評価額の3%(土地)または4%(建物)であり、登録免許税は土地・建物それぞれ不動産評価額の2%です。一方、相続時の不動産取得税は、土地・建物ともに非課税、登録免許税はそれぞれ評価額の0.4%となるため、生前贈与の方が税負担が大きくなります。(※令和9年3月31日まで)特に、固定資産税評価額が高い不動産を生前贈与する場合は、税額も高額になるため注意が必要です。
この2つの税金については、改正が頻繁に行われており、軽減措置などが受けられる場合がありますので、事前に確認しましょう。
生前贈与の注意点
当事者間に判断能力が必要
贈与者と受贈者が意思能力を持っており、両者の合意がある状態でないと生前贈与を行うことはできないことを説明してください。
生前贈与は、贈与をする人と贈与を受ける人の双方が意思能力を持っていることが必要になります。意思能力とは、法律行為において自分の行為がどのような結果をもたらすのかを理解できる能力を指します。例えば、高齢者が認知症などで判断能力を失っている場合、その人が行った生前贈与は無効とされる可能性があります。同様に、未成年者や精神疾患を持つ人なども、場合によっては意思能力がないと判断されることがあります。
意思能力がないとされた場合、その贈与行為自体が無効とされ、後に問題が発生する可能性があります。具体的には、贈与者が意思能力を持たない状態で行った贈与は、後に遺族や他の関係者がその贈与を無効にするための訴訟を起こすことができるのです。
このため、贈与者が高齢の場合や健康状態が不安定な場合には、医師の診断書などで贈与者に意思能力があることを証明しなくてはいけません。また、贈与を受ける側も贈与する人が意思能力を持っていることを確認し、後々のトラブルを避けるために文書で合意を記録しておくことが望ましいでしょう。公証人を通じて贈与契約を正式に作成することも、一つの方法です。
このように、生前贈与をトラブルなく進めるためには、贈与する人と受ける人がともに意思能力を有していることが基本的な条件となります。この点を十分に理解し、準備を怠らないことが、生前贈与を成功させる鍵となります。
死亡前3~7年の生前贈与は相続税に加算される
亡くなった人が死亡前3年以内(令和8年12月31日までに行われる贈与に適用)、もしくは7年以内(令和6年1月1日以降に行われる贈与から適用)に行った生前贈与は、相続税の課税対象財産に含まれる可能性がありますので注意が必要です。
これを「生前贈与加算」といいます。生前贈与加算とは、暦年課税制度による生前贈与を受けていた場合、この生前贈与財産を相続財産に加算して、相続税を課税する制度のことです。以前までは「死亡日以前3年間に贈与された財産は相続税の対象」とされていましたが、2023年度に税制改正が行われたことにより、「3年間」から「7年間」に変更され、2024年1月1日以降の贈与から適用されています。
これは死亡直前の相続税回避を目的とした贈与を防ぐために定められたもので、死亡日前3年以内、もしくは7年以内の贈与は相続税の計算上、無効となります。
ただし、死亡直前の贈与でも、そのすべてが生前贈与加算の対象とは限らず、贈与を受ける人によって適用の対象外となる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
贈与の取り消しは原則不可能
書面による贈与は、原則取り消すことができません。書面とは、贈与契約書はもちろん、内容証明郵便や調停調書など贈与の意思が明確に表れた書類すべてが該当します。
また、書面以外に口頭で行われた贈与であっても、すでに贈与が完了した部分については原則取り消しできず、返還を求めることもできません。
生前贈与は、手続きや税金を含め、しっかり納得した上で実行することが重要です。
ただし、書面・口頭ともに、詐欺・強迫・錯誤によるものや、未成年者・成年被後見人による単独行為の取り消しについては、贈与が完了していても認められます。
この他、贈与の取り消しについては民法に従って判断されますので、税理士や弁護士に相談するのが確実でしょう。