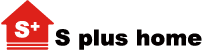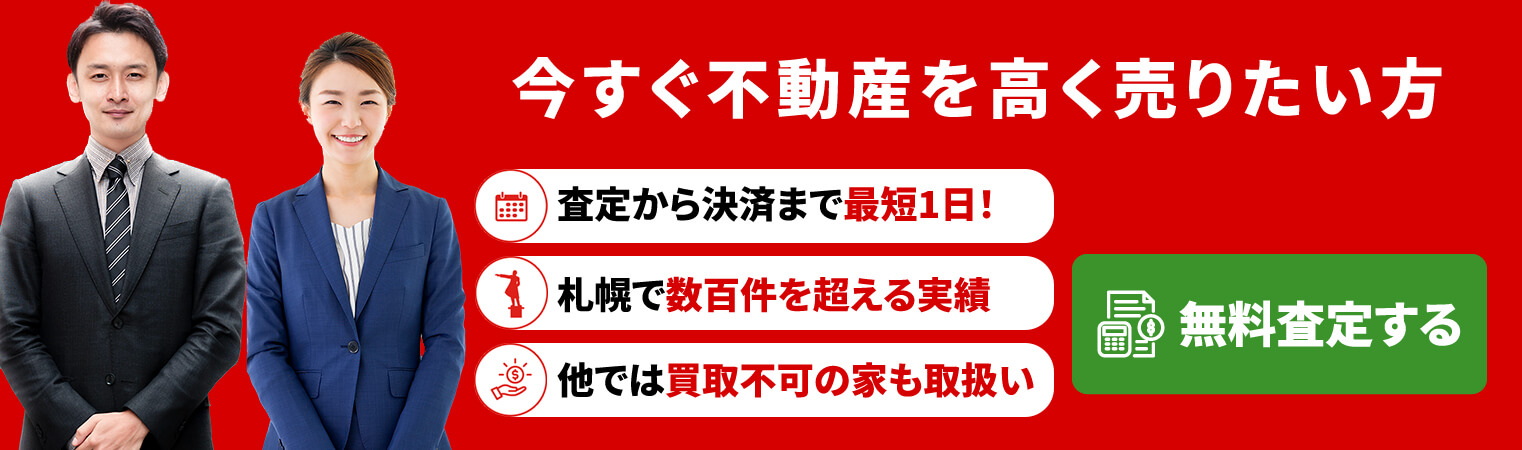「アパートを相続したら、その家賃収入は誰が受け取るの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
相続という状況になれば、相続人同士での分割協議や税金の手続きなど、考えるべきことがいくつも出てきます。
しかも家賃は月ごとに発生するものだけに、どのタイミングから相続人全員で分割すべきなのか、どうやって税金を申告すればいいのかなど、戸惑うポイントは少なくありません。
本記事では、相続したアパートの家賃の扱いから分割協議の流れ、そして税務面の基礎知識までを解説します。
早めに正しい情報を把握しておけば、家族間のトラブルや余計な税負担を避けながら、アパートを引き継ぐことができるでしょう。
相続したアパートの家賃収入は誰のもの?
相続したアパートの家賃は相続財産か
アパートの所有者が亡くなった時点で、そのアパートと家賃収入は「相続財産」に含まれます。
建物そのものだけでなく、入居者との賃貸借契約によって毎月発生する家賃も、遺産として扱われるのです。
ただし、相続人が複数いる場合は、誰がどの部分をどのように相続するか、きちんと話し合い(遺産分割協議)を行わないと、思わぬトラブルに発展するおそれがあります。
相続前の家賃
相続前に発生した家賃、つまり被相続人(亡くなった方)が生前に受け取るはずだった家賃は、原則として相続財産になります。
例えば、入居者が亡くなった方の生前に支払った家賃(亡くなる前の月分や日割り家賃など)は、亡くなった方の財産に含まれるため、後に相続人同士で分割対象となる可能性があります。
相続後~遺産分割前の家賃
相続が発生した後、遺産分割(誰がアパートを相続するか)を決定する前に発生する家賃は、共同相続人全員の共有財産となります。
実際には、相続人同士で「いったん代表者が受け取り、後で精算する」あるいは「一時的に別口座にプールしておく」などの方法で対応するケースが一般的です。
この段階で重要なのは、勝手に一人の相続人が家賃を使い込むようなことがないように、早めに話し合いをしておくことです。
そうすることで、後々の分配や税金の計算がスムーズに進みます。
遺産分割完了後の家賃
遺産分割協議がまとまり、アパートを相続する人(または共有者)が正式に決まった後は、その人が家主として家賃を受け取ることになります。
民法909条では、遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼると定められていますが、家賃収入は「将来の収益」にあたるため、この“さかのぼり効”は基本的に家賃には適用されません。
つまり、分割協議成立後に発生する家賃は、協議で決まった相続人が受け取ることになり、それ以前に発生していた家賃(共有状態の期間分)は、共有財産として相続人全員で分配する形が一般的です。
いずれにしても、事前に相続人同士できちんと話し合ってルールを決めておけば、不要な争いを避けられるでしょう。
アパート相続でトラブルを回避するポイント
単独名義で相続する
アパートを複数の相続人で共有する形になると、誰が管理や修繕の責任を負うのか、家賃の振り込み先をどうするのかといった細かい決定事項で意見が分かれやすくなります。
最悪の場合、話し合いが長引き、家賃が受け取れないまま滞ってしまうことも。
これを防ぐには、できるだけアパートを単独名義で相続する方法が有効です。
単独で相続することで、家賃の管理・運営もスムーズに行えるので、意思決定にかかる時間やトラブルのリスクが大幅に減ります。
ただし、相続税の負担が一人に偏るなどのデメリットもあるため、事前に相続人同士で十分に話し合い、理解を得たうで進めることが大切です。
遺言書を作成してもらう
遺産分割で揉めないために、被相続人(アパートの所有者)自身が生前に遺言書を作成しておくのは大きなメリットがあります。
遺言書があれば、「誰にどの物件を相続させるか」という意思が明確になるため、相続開始後に相続人同士で大きく意見が対立するリスクが下がります。
特にアパートは管理や家賃収入といった継続的な業務が伴うため、所有権を引き継ぐ人をはっきりさせておくことが重要なのです。
公正証書遺言など、法的効力の強い形式で遺言を残してもらうと、内容に争いが起こりにくく、安心して相続することができます。
事前に専門家に相談する
相続が発生しそうだとわかった時点から、税理士や弁護士、不動産会社などの専門家に相談しておくと、アパートの評価や相続税の見込み、さらには管理方法まで具体的なアドバイスが得られます。
事前に対策を検討しておけば、生前贈与や遺言書の作成、さらにはリフォームや管理方法の見直しなど、状況に合わせた最適解を見つけやすくなるでしょう。
プロのサポートがあることで、手続きの煩雑さや相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
アパート相続後にすべきこと
確定申告
アパートを相続した場合、まず気をつけたいのが税務面の手続きです。
亡くなった方の確定申告(準確定申告)と、相続人の方で行う確定申告の二つをチェックしておく必要があります。
準確定申告
被相続人(亡くなった方)が1月1日から死亡日までの間に得ていた所得については、相続の開始を知った日から四か月以内に「準確定申告」を行わなければなりません。
もし被相続人がアパート経営による家賃収入を得ていた場合、その分の所得も申告に含める必要があります。
相続人の確定申告
アパートの家賃収入が相続人に引き継がれた後は、新たにオーナーとなった方の不動産所得として、翌年の確定申告で申告しなければいけません。
分割協議がまだ終わっていない場合でも、家賃が発生している間は共有状態として所得を按分したり、代表者がいったん受け取って後ほど精算するなど、状況に応じた対応が求められます。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日から十か月以内と比較的短いので、準確定申・相続税の手続き双方を混同しないよう、早めに税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
入居者への通知
相続によりオーナーが変わった場合、入居者に対して「誰が新しい貸主(家主)になるのか」を早めに伝えることが重要です。
通知のタイミング
相続が発生した段階で、入居者に混乱を与えないためにも、分割協議の見通しやオーナー決定の状況が分かり次第、なるべく早く連絡するのが望ましいでしょう。
家賃の振込先などが変わる場合は、とくにすぐ案内できるよう準備しておくことが大切です。
通知の方法・内容
書面や口頭での案内のほか、賃貸借契約書の更新手続きなどを通じて行う場合もあります。
入居者に安心感を与えるためには、「相続でオーナーが変わったこと」「管理体制や緊急連絡先がどうなるか」「家賃の支払い方法に変更があるか」といったポイントを明確に伝えましょう。
連絡先がはっきりしていれば、建物のトラブルや修繕依頼など、通常の管理業務もスムーズに運びやすくなります。
相続によるオーナー変更は入居者にとっても大きな影響を与える可能性があります。
丁寧に通知を行い、疑問や不安を解消できるようにしておくことで、トラブルを防いで円満にアパート経営を続けることができるでしょう。
相続したアパートの家賃を円滑に引き継ぐには、遺産分割協議や税金手続きを正しく進めることです。
オーナー変更の連絡を入居者に早めに行い、管理体制や家賃の振込先などを明確にしておけば、トラブルを防いでアパート経営を続けられます。
プロに相談しながら、家族全員が納得できる形で相続を完了させましょう。